| 交通事故の死傷がもたらすインパクト |
| 要約|調査の目的|方法|参加した組織|結果|結論|法律制定への提案 |
交通事故被害者およびその家族・遺族が被っている生活の質の低下
および生活水準低下の基本的原因についての研究
改善への提案
欧州交通事故犠牲者連盟(FEVR)
原文ページ
著者:Marcel Haegi and Brigitte Chaudhy
Exsecutive summary
翻訳:今井博之
( Oct. 27, 2002 )
この研究は欧州連合(EU)との共同研究として実施された。
1995年2月 |
欧州交通事故犠牲者連盟(FEVR)が行なった以前の研究によって、交通事故遺族だけではなく交通事故犠牲者本人とその家族は、生活の質や生活水準の急激な悪化を経験していることが明らかになっている。
本研究は、こうした悪化の原因を明らかにし、改善のための解決策を提案することを目的にして考案された。欧州の9カ国それぞれを代表する16の犠牲者組織に所属する約1万の遺族・犠牲者本人およびその家族に対し詳しいアンケートを送付した。
最重要だと思われる知見は、以下の通りであった。
| 1. |
交通事故の犠牲者に知らせるべき法的権利や支援組織に関する情報は、きわめて不十分である。 |
| 2. |
犠牲者やその家族のほとんどが、精神的・実務的・法的なサポートを必要なものと考えており、その要求は相当な強さである。 |
| 3. |
そして刑事・民事両方の法的システムに対して広範な不満を表明している。 |
| 4. |
頭部外傷の頻度は希ではないにもかかわらず、そのために長期間にわたり障害が続くという事実を司法は認識していない。 |
| 5. |
犠牲者やその親族がこうむっている精神的苦悩は、しばしば極限に達しており、長期にわたっている。また、時間の経過とともに強くなり、死期を早めるほど深刻な場合も少なくない。 |
アンケートでは、自分の考えを書き加えてもらい、 改善のためにどうすればよいと考えているかを調査したが、ほとんどの人が単刀直入かつ明快に意見を述べられて、それによってこの研究が、より実りあるもの になった。いくつかの国では既に実施に移されたものもあるが、ここでは、司法上の改善策のリストなど現実的な提案を行ったので、早急かつ直ちに全ての欧州 各国政府が実施にうつされることを希望する。
|
以前に行われた「交通事故犠牲者およびその家族が 被っている身体的・精神的・経済的二次被害についての研究」[1]では、死亡者の遺族(以後、単に「遺族」とする)や後遺障害となった者の家族(以後、単 に「家族」とする)のそれぞれ90%と85%が、生活の質の相当な悪化が続いていることを表明しており、しかもそのうちの約半数は激烈なものであることを 明らかにした。さらに、遺族の50%、本人および家族の60%が、深刻で、劣悪な生活水準の低下が長期間にわたって続いていることを明らかにした。
これらの結果は、交通事故の遺族や家族が被っているインパクトがこれまでの想像以上に激烈なものであり、障害者となった犠牲者の後遺症が重症であること を明確にする内容であった。また、こうした個々の悲劇によって国家がこうむる社会的コストや社会資源に及ぼす長期的な経済的影響が膨大なものであることを 示した。
今回の調査の目的は、遺族や家族が生活の質と生活水準の両面において低下を被っている原因を特定し、行政上、司法上の改善策を提案することである。
すでに明らかになっているとおり、遺族や家族が被っている極限の苦悩は、早急な注目と治療に値するものである。交通事故のもつインパクトの激烈さを、社 会や司法が、気付き、認めなければならない。犠牲者は法的な援助を必要としており、司法手続きは違反の軽重や結果の重傷度を反映したものでなければならな い。民事手続きについても、より早期の決着をはかるために簡素化されなければならない。犠牲者やその家族に対する補償は、生活水準の低下が起こらないこと を保証するために引き上げられなければならない。
また、国中が、全欧州の人々が、交通事故という悲劇の大半は防止できるはずであるという認識を高め、従って教育や取締りの強化、その他可能なすべての対策を通じて交通事故の危険を減らすためのコンセンサスを高めるために、この調査結果が役立つであろう。
|
犠牲者の生活の質および生活水準の低下の原因を特定するために、無記名で、56項目からなるアンケートに答えてもらった。56項目は、以下の基礎調査とA~Gまでの8つの大項目にまとめられる。
基礎調査
犠牲者やその家族の分類普A年齢、事故の発生年月日、など...。
A. 初期の支援と情報
事故の後に接触を持った多種のサービスで、適切な支援や情報が得られたかどうか。
B. 刑事訴訟
自分の事例では、刑事上の正義が実行されたと思うか否か。また、どのように扱われ、改善する余地は何だと思うか。
C. 保険・民事訴訟
保険会社とのやり取りを記載してもらい、支払われた補償が公正であったかどうかについての自分の意見を述べてもらう。裁判になった事例については、金銭面 での正義が果たされたと思うかどうかと、民事訴訟の期間の長さはどうだったか、改善する余地は何だと思うか。
D. 犠牲者に対する医療
負傷者の現在の身体状況を明らかにすることと、医療やリハビリに満足であったかどうかを聞いた。また、頭部外傷の例では、質問項目を追加した。
E. 犠牲者やその家族に及ぼした肉体的・精神的影響
犠牲者や遺族・家族がこうむった精神的・肉体的二次被害について調べた。ただし、受傷した本人の事故による直接的身体的負傷は除いた。こうした二次被害は、しばしば重症で長期にわたるにもかかわらず、裁判や保険会社からは概して無視されている。
F. 生活のその後の状況
事故によって自分の生き方がどういうふうに変化したかの概要を書いてもらい、向精神薬を飲んだかどうか、家族・友人・職場の同僚などとの関係がどうなったか、生活を楽しむゆとりがどうかについて聴いた。
G. 仕事のその後の状況
事故によって自分の仕事にいかなる変化がもたらされたか。
アンケートは、遺族や家族の生活の質や生活水準に影響を及ぼすと考えられる状況のほとんどをカバーすることを意図したので、従って、この研究に参加した組織に、前述したそれぞれの大項目ごとに質問のリストを提出するよう要請した。
数百におよぶ質問内容案が集められ、詳細に検討された。次第に数がしぼられて、アンケート案を作り、それぞれの組織に送って、限定的・試験的に実施され た。質問内容が容易に理解されるように、簡単な言葉が選ばれた。結果として56項目が残ったが、各事例は特有の事情があり、あらかじめ決められた様式では 重要な問題が見過ごされる可能性があるので、それぞれの大項目の最後に、自由記載のコメント欄を設けた。
英語で作られた最終案が、フランス語、ドイツ語、イタリア語、フラマン語、オランダ語、ギリシャ語のそれぞれに翻訳された。アンケートは、それぞれの国 の組織が作った趣旨説明の手紙を添えて、犠牲者およびその家族に郵送された。アンケートを送るのに、可能な限り中立的な方法になるよう注意が払われた。全 ての単語が同じ意味に対応しているわけではないので、英語を他言語に正確に翻訳することはたやすいことではなかったが、しかし、これは多言語にわたる調査 では常に内在する問題である。
|
この調査に参加した組織は、以下の通りである。全て、欧州交通事故犠牲者連盟に所属する組織である。
| ・Association de Parents pour la Protection des Enfants sur la Route (ベルギー) |
| ・Association de Parents pour la Protection des Enfants sur la Route, régions Wallonnes (ベルギー) |
| ・Association des Familles des Victimes de la Route (スイス) |
| ・Association des Familles des Victimes d'Accidents de la Circulation (フランス) |
| ・Association des Victimes de la Route (ルクセンベルグ) |
| ・Associazione Italiana delle Famiglie delle Vittime della Strada (イタリア) |
| ・Campaign Against Drinking and Driving (イギリス) |
| ・Dignitas (ドイツ) |
| ・Ligue Contre la Violence Routière (フランス) |
| ・Parents d'Enfants Victimes de la Route (ベルギー) |
| ・RoadPeace (イギリス) |
| ・Strada Amica, Associazione Italiana per la Tutela della Vita sulle Strade (イタリア) |
| ・Strada Amica, Associazione per la Sicurezza degli Utenti Deboli (イタリア) |
上記の組織は本質的に、交通事故犠牲者やその家族、友人、関係者の団体である。これらの団体の目的は、以下のとおりである。
| a. |
犠牲者に心理的・法的・実務的援助を提供し |
| b. |
暴走、怠惰運転、飲酒運転、交通違反などの反対運動によって、交通事故の防止に貢献する。 |
また、下記の団体は、本連盟に所属する組織ではないが、この研究に参加した。
| ・Centre of Research and Prevention of Injuries among the Young (ギリシャ) |
| ・Institute of Social and Preventive Medicine (ギリシャ) |
| ・L.O.S./A.N.W.B. (オランダ) |
一番目の団体は、アテネ大学医学部の研究センターで、後2者 は、犠牲者への援助団体である。この2組織は、本連盟加盟団体と違って、犠牲者当事者団体ではないので、犠牲者当事者のアプローチの仕方や回答とは違って いるかもしれない。しかし、抽出対象が違うにもかかわらず、他の調査でも傾向が一致していることが示されている。
犠牲者全体という点で抽出方法に問題があったかもしれない。抽出はわざと無作為にではなく、組織に参加している者、その友人、および近い人々の中から選ばれた。
このような組織に参加しようという主たる動機は、利他主義に基づくものである。つまり、犠牲者およびその家族は、自分たちが得た援助及び、得たかった援 助を、みんなと分かち合うことを望み、個人的経験を通して交通事故の危険性を特別に認知していることから、このような危険性を減らすための行動に参加した いと思っているのである。事故の個別の事情や、司法とのあるいは保険会社との問題やそれによる苦悩の程度は、この研究に参加しようと決断した主要な要因で はなかったと思われる。その証拠に、これらの組織の構成員は、負傷すらしていないか、軽傷の犠牲者をも含んでおり、かつ、一方で、死亡事故の遺族や重度の 後遺症を残した犠牲者であるのもかかわらず、どの組織にも参加していない者がいることからもわかる。これが、これらの組織の構成員から抽出してアンケート をとっても統計学的信憑性をゆがめるものではないと考えられる理由である。考察のところで、この点については、さらに言及している。さらに、本研究は、質 的な内容を理解することを主眼においたものであり、正確な定量を目的としたものでは無いことを強調しておきたい。
|
回答のあった1,364のうち、59%は遺族からのもので、41%は 事故で障害者となった本人またはその親族からのものであった。通常のこの種の統計解析で、このぐらいの規模であれば、統計的誤差は±5%とみなされてい る。以下、必要に応じて、遺族と後遺症となった者との差異も検討した。
A.初期の支援と情報
遺族の91%、親族の78%という、圧倒的多数が、犠牲者家族が有する法的権利、つまり、質問をする権利、照会にあたっての代表としての権利、死者の第二 当事者としての権利、提訴できる有効期限などなど、についての十分な情報は、与えられていなかった。遺族・親族の約85%は、援助についての情報あるいは 犠牲者組織についての情報が与えられていなかった。(図5)
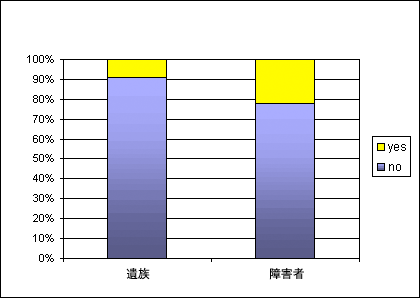 |
| (図5) |
交通事故の犠牲者となるのは、しばしば若者であるが、移植のドナーが不足しているという公共の認識にもかかわらず、遺族のうちたった10%にしか臓器提供のアプローチがされていなかった。(図6)
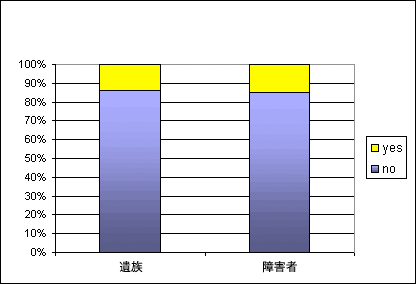 |
| (図6) |
遺族や親族が必要と感じている援助は、
| ・ |
死亡したという知らせは、その種の仕事としての訓練を受けた専門家によってなされるべきである、 |
| ・ |
最愛の者の亡骸に一刻も早く接触できること、 |
| ・ |
直後から始まり、しばしば長期に及ぶことがある情緒的・心理的・実務的・法的な支援が専門家によってなされること、 |
| ・ |
法的権利、法的手続き、照会手続き、犠牲者団体などの支援組織、事故の詳しい状況説明などは、直ちに知らされるべきである、 |
| ・ |
法的アドバイス |
B.刑事処理
刑事上の処理についての不満は、最大であった。遺族の89%、親族の68%が、自分の例について正義が実行されなかったと表明している。また、遺族の 75%、親族の61%が、罰則は軽すぎたと表明している(図7,9,45)。さらに、70%近くの者が、自分たちの事例の扱いは適切ではなかったし、真剣 に取り組まれなかったし、敬意をもって接してもらえなかったと述べている。
遺族・親族が表明した要望で最も多かったのは、
| ・ |
事故を起こしたドライバーからは、アルコールや薬物の濃度を検査できるように強制的に採血をして欲しい、 |
| ・ |
事故の捜査や起訴手続きは、殺人事件と同様のレベルで行って欲しい、 |
| ・ |
死傷事故を起こした場合、ドライバーの免停期間を、少なくとも裁判まで延長して欲しい、 |
| ・ |
訴訟の過程に遺族や親族を参加させること、 |
| ・ |
手続きの過程で敬意をもって扱ってもらえること、 |
| ・ |
悪質な違反によって死傷事故を起こしたような事例では、もっと厳しい判決と、しかるべき禁固期間、あるいは今とは違った処罰の方法が必要である(図10,11)。 |
| ・ |
違反の常習者には生涯運転禁止とすべき。 |
C.賠償保険と民事処理
保険会社に対する広範な不満も明らかになった。80%近い遺族・親族は、保険会社の対応と賠償額に不満を表明している(図12,15,16,53)。60%近くの者が、保険会社が強制的に要求した死体検案にたいする不満を表している。
95%という圧倒的多くの遺族・親族は、犠牲者およびその親族のための民事訴訟に関係する弁護士と事故の直後から接触を持つことは望ましいことであると考えている(図17,18)。
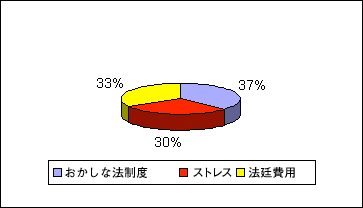 |
| (図18) |
要望のうち、最も多かったものは、
| ・ |
葬儀の支出、家計の減収や治療費などのコストなどについては、犠牲者本人やその家族が困窮しないように、保険会社が直ちに、とりあえずの前払いを行うべきである、 |
| ・ |
保険会社の掛金や支払い定款を早急に改善すべきである。 |
D.負傷者に対して行われた医療
事故で障害者となった者のうち約半数は、事故後3年後に症状が固定した。残る半数は、症状の固定はそれ以後、または、今も固定していないという。保険会社 によって認定された身体障害状況について公正ではないと考えている者が約60%であった。40%近くの者が、医療やリハビリに対する不満を表明している。
頭部外傷を負った者では、事故後3年で完全に元に戻った者は37%に過ぎず、3年以上経過して元に戻った者も19%しかない。残る44%は、永続的な神 経障害・脳障害を残している。交通事故のうち約半数は頭部外傷でることを考えれば、このことは特に重大な問題である。頭部外傷患者の約40%が神経学的治 療やリハビリに対して不満を表明している。
事故後の3年間は、頭部外傷患者は次のような症状を伴う:記憶力や集中力の障害(78%)、通常の業務を遂行できない(70%)、言語障害(59%)、などである。3年以上経過すると、これらの数字は、それぞれ61%、52%、29%にまで低下する。
この調査結果は非常に重要な事実を明らかにしている。
| ・ |
交通事故によって被った肉体的・知的な障害は長期間に及ぶことがあり、犠牲者が自分の生活水準を維持するための能力まで奪われるほどのものである、 |
| ・ |
頭部外傷の悪影響は、外見的に必ずしも明らかではないので、周囲からは認知されにくい面を持っており、仕事や各種資格を喪失することさえ起こることがあり、社会全体に及ぼしている経済的損失は深刻である。 |
E.犠牲者本または遺族・親族に及ぼす肉体的・心理的インパクト
犠牲者には次のような肉体的症状がある:睡眠障害(49%)、頭痛(55%)、ひどい悪夢(41%)、全般的健康障害(58%)。3年以上経過しても症状 の頻度は減少せず、恒久的なものではないかもしれないが、長期間に及ぶことが示されている(図25)。
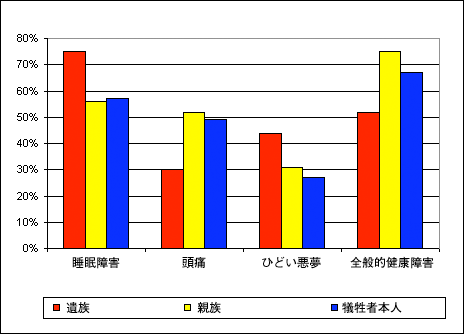 |
| (図25) |
犠牲者本人はもとより、遺族や親族の大多数が精神疾患を患っ ている(図26)。最悪の状況は遺族にみられる。最初の3年間は、職業としての仕事、家事、調理、勉強などの日常生活の業務に対する関心を喪失する (72%)、自動車を運転できなくなる(70%)、自信を喪失する(49%)、不安発作に悩まされる(46%)、自殺念慮(37%)、うつ状態になる (64%)、恐怖症になる(27%)、摂食障害(35%)、怒り(78%)、はげしい無念の感情(71%)、などである。3年以上経過しても、これらの数 字は平均で10ポイントしか低下しない。つまり、これらの影響は長期間に及び、場合によっては生涯続く場合もある。特に、自殺念慮は37%から26%へ変 化するにすぎず、多くの遺族や親族を極限の窮地に立たせ続けている。
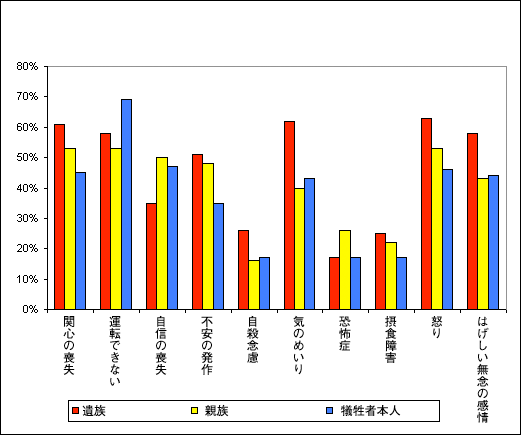 |
| (図26) |
自殺念慮を除けば、障害者となった被害者の親族の心理的状況 は遺族のそれとほとんど同じパターンを示している。驚くべきことに、障害者となった犠牲者本人は、肉体的な疾患などを抱えながらも、精神的には親族よりも ましな状況にある。特に、不安発作、恐怖症、摂食障害、怒り、激しい無念の感情、などについて、そうである。
前述したように、遺族の場合は、最悪の状況にある。対人関係の問題、意思疎通の困難、性生活の問題などは、70%に及ぶ。これらの数字は、障害者の親族 で40%、障害者自身が50%である。3年以上経過しても予想に反して減少傾向が見られず、むしろそれぞれの項目で5ポイントの悪化が見られる(図 27)。
遺族が最初の3年間に得ることができる援助は、87%が家族のものから、80%が友人から、40%が医者から、23%がプロのカウンセラーから、9%が 雇用主から、5%がグループ治療によって、となっている。障害者となった犠牲者本人とその親族は概ね同じ傾向であるが、遺族よりも医師や家族のものからの 援助の割合が高くなっており、これは、それらの人との接触の機会がより親密であることに起因するのであろう。3年以上経過すると、援助の必要性が数ポイン ト増加する(図29)。
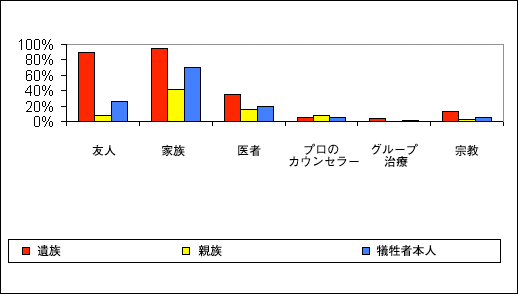 |
| (図29) |
F.その後の生活に対する影響
障害者となった本人および親族の約50%は、事故の後、精神安定剤・睡眠薬・タバコ・酒・麻薬などの向精神作用のある薬物の使用量が以前より増えたとい う(図31)。もし、これらの消費量が増えたことが、今後の事故の増加につながる可能性があるとすれば、悪循環を形成する。
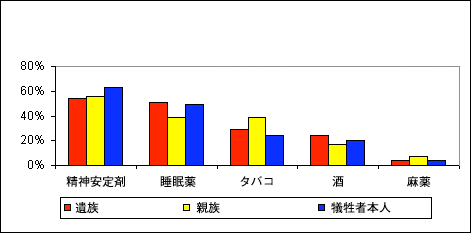 |
| (図31) |
惨劇は、その人と、その周囲の正常なパートナーとの関係を悪 化させる場合があることが知られている。この問題を調べた質問では、それは必ずしも真ならずという結果であった。友人との関係についてどうなったかを調べ たところ、遺族では、「変化しなかった」(36%)、「良くなった」(21%)、「悪化した」(23%)。配偶者との関係は、「変化しなかっ た」(34%)、「良くなった」(16%)、「悪化した」(21%)。同僚との関係では、「変化しなかった」(45%)、「良くなった」(6%)、「悪化 した」(16%)、という結果であった。障害者となった犠牲者本人およびその親族では、これらの関係は「変化しなかった」が多数を占めたが、「変化した」 と答えた例では、「良くなった」という方が多かった。
事故の後、遺族の49%、親族の47%になんらかの世帯状況の変化がみられた。遺族では、別居(6%)、離婚(5%)、子どもが家を出た(28%)、転居した(33%)、となっていた。本人およびその親族では、別居と離婚の割合はこれを上回っていた。
遺族では、「事故後3年間は将来の計画を立てるということは不可能であった」とするものが68%もあった。3年以上たっても、なお59%の者がその状況 にとどまっていた。障害者となった者の親族では、まだ状況はましで、さらに障害となった本人は、さらにそれほど悲観的ではなかった(図35)。
遺族にとって、「事故後3年間は以前のように生活を楽しむということは全く無縁の状況であった」と答えたものは91%にも及んだ。事故後3年以上経過し ても、なお84%の遺族が同様の状況が続いていた。多くの者にとって、これは永続的なものとなるであろう。同様の答えをした障害者親族は68%、障害者本 人は69%で、遺族よりはましであった。さらに時間が経過しても親族での数字は変化しなかったが、本人ではさらにましになっていた。しかし、本人でも回復 したのは15%であった(図36)。
G.その後の仕事にたいする影響
事故後に仕事を変えた遺族・親族・本人のそれぞれ60%・80%・70%が、「周囲の状況からそうせざるを得なかったからだ」と答えている。事故後に失業 した者のうち、それぞれ65%・33%・33%が精神敵・心理的原因でそうなったといい、残りは身体的理由であったという。
|
この調査を通じて明らかになった苦悩状況は、交通事故の結 果、この社会の中で悲惨な生活を送っている人々の割合が今も増加し続けているということを示している。司法システムを含め、行政当局になかなか理解しても らえない事柄として、交通事故の遺族および障害者となった親族は、殺人や犯罪などの被害者の家族と同様、しばしば生涯に及ぶ苦悩にさいなまれて続けている ということがあげられる。なお、さらに今でも援助は事実上無きに等しく、適切な補償も無い。
本研究の目的は、犠牲者本人およびその家族の者が最も切実に緊急に求めている要求を提示し、それらの者の苦悩を和らげるため、社会的疎外や不公正を予防するため、生活の質や生活水準の低下を食い止めるための適切な対策について提案することにある。
以下、そのような要求・解決策が明らかになった。
| ● 情 報 |
事故後の照会、保険会社との対応の方法、民事訴訟について、被害者組織や支援組織、カウンセリングなどの情報を含めて、事故の状況についてや法的権利、法的手続きについての情報に直ちにアクセスできること。
このような情報が記されたパンフレットが、警察から間違いなく手渡されること、救急機関、病院、裁判所などで自由に手に入れ ることができること。そして、それらの印刷や配布にかかわる費用はしかるべき政府機関によってなされるべきで、さらに、交通事故の犠牲者と接触する全ての 機関の教育プログラムを作成すべきである。警察は、事故の詳細と捜査の進行状況について、犠牲者本人やその家族の者に定期的に情報を教えなければならな い。 |
| ● 援 助 |
精神的・実務的・法的支援が緊急に求められている。
犠牲者に対する無料の「援助センター」が考えられる。このセンターは、犠牲者に司法分野・医療分野・精神的分野での援助やア ドバイスを提供する。犠牲者のボランティア組織が行う犠牲者援助活動は、政府から資金援助がなされるべきである。死亡事故や重傷事故の場合は、事故の直後 から、犠牲者およびその家族に対して民事訴訟にかかわる弁護士を決めておくべきである。 |
| ● 刑事問題としての公正性 |
死傷事故を起こした場合の交通違反に対する罪状は、死亡したことあるいは負傷したという事実を中心的な問題として扱わなければならない。必要ならば、死亡 あるいは負傷という事実に対して問題を解決できるように法律を改正しなければならない。判決は抑止力をもつような十分に厳しいものでなければならない。死 亡あるいは負傷という事実を認めたということの証としてもっと別な処罰の方法を検討すべきである。
現行の刑事司法システムを公平にすべきである。現行は加害者に有利なシステムであり、もっと犠牲者の訴えや要求を考慮に入れ るべきである。犠牲者は、今後もはや刑事司法手続きから排除されることなく、刑事裁判のしかるべき当事者として完全に認められるべきである。刑事裁判の当 事者として手続きに参加し、情報を得ることは、これまで多くの犠牲者が民事裁判で直面してきた多大な困難を予防することになる。 |
| ● 保険会社に対する不満・民事訴訟 |
保険会社とのやりとり、提供される補償額に関して広範な不満の声がみられ、特に、重傷例や死亡例で顕著であった。犠牲者やその家族は、裁判が長引くこと と、保険会社の無神経さにひどく苦しめられている。民事裁判訴訟は、しばしば刑事訴訟の代理であると見なされている。
葬儀代金などの支出をカバーするための即金を、保険会社が直ちに支払うよう義務づけるべきである。また、収入を絶たれて苦し んでいる犠牲者家族のためには、前金も支払うべきである。補償のレベルは被った被害に応じたものでなければならず、真の実状を正確に把握するために定期的 な見直しが行われるべきである。
民事訴訟は、簡略化と迅速化がはかられるべきである。二次被害ということも考慮されなければならない。民事訴訟は刑事訴訟の代替えではなく、そのように思わせてもならない。
犠牲者の頭部外傷について理解を深め、彼らが可能な限り正常な生活を維持できるための適切な問題解決となるように、あらゆる手をうつべきである。 |
| ● 犠牲者およびその家族に及ぼす精神的・身体的影響 |
近親者の突然の痛ましい死は、残された家族の者の人生に深刻な影響をもたらす。多くの場合、遺族は生活への関心を失い、自殺念慮を経験し、実際に自殺する 者もいる。ショックとその後も続くストレスは免疫機能の障害をきたし、病に陥るか、さらに死に至る場合さえある。自殺念慮を除けば、犠牲者本人と、その家 族とでは、被っている悪影響はほとんど同じである。
これらの問題が示しているのは、犠牲者の家族に対して長期的な心理的サポートが切望されているということである。このような 援助は、現行では主として友人や家族の者から与えられているが、本来は前述したように「援助センター」によって補足される必要がある。こうした苦悩が生活 の質を低下させている大きな原因であるが、副次的な影響であると見なされて、現時点では法的には被害として認められていない。 |
|
以下は、重要なポイントを列記したもので、われわれの思いとしては、交通事故犠牲者の立場に立った法律を今後作成する時に加えるべき内容であると考えている。カギ括弧の数字は、その項目の内容を既に採用している国があるので、参考文献としてあげた。
| 1. |
医学・心理学・社会学・法学の領域の援助やアドバイスが無料で得られるような公的なセンターを新設すること。スポンサーであるボランティア組織は既にこのような援助を行っているが、さらにこのようなセンターが必要なのである。[5,6] |
| 2. |
死亡後の、あるいは負傷後の、あらゆる手続きに同伴し、代理人となって、犠牲者や家族が、自分たちは援助されている、自分たちの権利を教えてもらい、その権利が守られていると感じられるように、信頼できる人をつけること。[7,8] |
| 3. |
現実に起きている損害を補償できるようにするために、賠償レベルを引き上げ、定期的に見直すこと。 |
| 4. |
すべての犠牲者が現実の被害補償を受けられるようにする。そのために、例えば保証基金の効率的運用を行うなどの方策をとる。 |
| 5. |
頻度の高い脳外傷という身体への傷害に対して賠償を拡大すること。脳外傷は、繰り返し再発する精神機能障害から永続的な後遺症としての精神機能障害まで幅がある。 |
| 6. |
葬儀費用・収入の喪失・医療費などをカバーするために、保険会社が犠牲者やその家族に対して前金(当座補償)を支払うことを義務づける。[7] |
| 7. |
犠牲者やその家族を刑事訴訟手続きに参加させ、民事訴訟においても十分な情報を得ることができて、迅速に解決されるようにするだけでなく、民事裁判において資格のある関係者のすべてが損害の申し立てを実行できるように援助すること。[5,7] |
| 8. |
司法制度のバランスを取り直すこと。現行の制度は、過剰ともいえる被告中心主義であり、被害者側にも平等の権利を保障すべきである。そうすることによって被告の家族だけでなく犠牲者や犠牲者側の家族の要望にも答えることができる。[5] |
| 9. |
被告にも賠償の一部を負担させることを考慮すること。判事が、被害者に直接援助をするために加害者の収入や財産の一部を差し押さえることができるようにすべきである。さらに、被害者にかかった裁判費用や医療費の請求を直接加害者に求めることもできよう。[5,7,8] |
| 10. |
著しい怠慢や基本的交通規則の無視にもとづくような違反は、未必の故意という刑事法上の罪として扱うこと。スピード違反や信号無視、飲酒運転などがこれに含まれるであろう。 |
| 11. |
迅速で効率的な「援助センター」を普及させること。これらのセンターは、交通事故犠牲者のための無料緊急ホットラインを備えているばかりではなく、無線で連絡をとりあって制御されている救急車やヘリコプターを備えている。 |
| 12. |
暴力的犯罪の被害者の補償に関する欧州会議をヨーロッパの全ての国に拡大すること。[9] |
|
